焙煎士とは、コーヒー豆の“味と香り”を決定づける焙煎という工程を担う職人のこと。生豆の状態や品種、産地ごとの特徴を見極め、温度と時間を巧みにコントロールしながら、最適な焙煎度合いに仕上げていきます。
資格は必須ではありませんが、SCAJ認定「コーヒーマイスター」などの民間資格を取得することで知識や技術を体系的に学ぶことができます。
仕事内容は焙煎だけでなく、カッピング(風味の評価)や豆の選定、在庫管理、商品開発まで多岐にわたります。焙煎士の世界は奥深く、最近では俳優・坂口憲二さんのように“表舞台”から“焙煎の世界”へ転身し話題となるケースも。
この記事では、焙煎士の基礎知識から必要なスキル、有名焙煎士の事例まで、初心者にもわかりやすく解説します。
特別価格でまとめ買いできるチャンス!
- 全品スペシャルティコーヒーで味も香りも本格派
- 常温・暗所で数か月保存OK!まとめ買いしても安心
- AGF・ドトール・ネスカフェ・UCCなど人気ブランド多数
1杯20円の激ウマ高レビューコーヒー
\コスパ重視派に/
ダイエット中のあなたに最適!
\内側からスッキリ!在庫切れ必須/
ハマる人続出!クセになる味わい
\ばかうまスペシャルティコーヒー/

「毎日のコーヒー、なんとなく味気ないと感じていませんか?苦味が強くて、なかなか楽しめない…。
そんなあなたにぴったりなのが、『きつね珈琲』です。フルーティーでやさしい味わいは、まるで果物を食べているような感覚。
『きつね珈琲』はまだ開設前ですが、LINE登録していただくと、限定の割引クーポンや、無料でコーヒー豆をプレゼントするチャンスが!
\割引クーポンや無料コーヒー豆をゲット!
オープン前なので登録してお待ちください/
執筆者情報

【執筆者情報】片山 勇大
焙煎士・コーヒーインストラクター2級
きつね珈琲メディア運営者。1997年生まれ、三重県在住。元プログラマーとして働く中でうつ病を経験し、退職後はライターやSEOディレクターとして活動。コーヒーに癒やされた原体験をきっかけに、独学で焙煎を学び「きつね珈琲焙煎所」を立ち上げる。現在は、食品衛生責任者とコーヒーインストラクター2級の資格を活かし、自家焙煎豆の販売やレビュー記事の執筆、SNS運用を行いながら、Shopifyを活用したオンラインショップを展開。「手をかけた味」を届けるため、焙煎・梱包・発送まで一貫して自身で担当している。コーヒーの魅力を多くの人に伝えるべく、実務経験に基づいた透明性のある情報発信を心がけている。

アラビカQグレーダー/エンジニア
きつね珈琲メディア 監修。1998年生まれ、小田原在住。 普段はエンジニアとして働きながら、大好きなコーヒーの活動に力を入れている。これまでに日本最大級のコーヒーイベント SCAJに出店したり、間借りでカフェを開いたりと、幅広くコーヒーの現場を経験してきた。現在は カフェクラウディアと共に、「コーヒーの楽しさ」を伝えるための活動をしている。
焙煎士とは
焙煎士(ロースター)とは、生豆を焙煎してコーヒーの香りや味わい、そして個性を引き出す専門職のことを指します。
焙煎は「コーヒーの味を決める最後の工程」とも呼ばれ、同じ豆であっても焙煎士の技術や感性によって風味はまったく異なります。
豆の種類や産地、収穫時期、湿度、気温など、あらゆる条件を考慮して焙煎プロファイル(温度と時間の管理)を設計し、焙煎中も色・香り・音の変化を繊細に感じ取りながら調整していきます。
焙煎士の仕事は単なる作業ではなく、「科学」と「芸術」の融合に近いものです。メイラード反応やカラメル化といった化学的変化を理解しつつ、酸味・甘味・苦味・コクのバランスを創造する感覚的な技術も必要とされます。
そのため、焙煎士には理論的な分析力と感性の両方が求められます。
近年では、焙煎士の個性や哲学がブランドのアイデンティティを形成するケースも増えており、焙煎士は“コーヒーの作り手”から“物語の語り手”へと進化しています。
焙煎士とバリスタの違い
焙煎士とバリスタはどちらもコーヒーに深く関わる職業ですが、その役割は大きく異なります。焙煎士はコーヒー豆を“つくる人”であり、バリスタはその豆を“提供する人”です。
焙煎士は生豆を扱い、熱と時間をコントロールして豆本来のポテンシャルを最大限に引き出します。一方、バリスタは焙煎された豆を使用し、抽出技術によってその味を再現します。
焙煎士が「素材をデザインする職人」だとすれば、バリスタは「作品を演出するアーティスト」と言えます。優れたバリスタは焙煎士の意図を理解し、豆の個性を最大限に活かした抽出を行います。
反対に焙煎士は、バリスタからのフィードバックをもとに焙煎を微調整します。両者の関係は上下ではなく、対話と協働によってコーヒーの完成度を高めていく“パートナー”のような関係です。
焙煎士の有名人
日本には、世界的にも知られる焙煎士が多く存在します。彼らは美味しいコーヒーを作るだけでなく、「焙煎」という行為そのものを文化や哲学の領域にまで高めています。
ここでは、焙煎士という職業を一般に広めた著名な3名をご紹介します。いずれも焙煎技術の高さだけでなく、コーヒーに対する思想や発信力によって国内外で影響力を持つ人物です。
彼らに共通するのは「焙煎を通して世界とつながる」という姿勢です。豆の産地へ直接赴き生産者と対話を重ねたり、世界大会で日本の焙煎文化を発信したりするなど、焙煎士の仕事が“店の中だけ”にとどまらないことを示しています。
焙煎は科学的な側面を持ちながらも、感性と哲学が交差する世界です。ここで紹介する坂口憲二さん、後藤直紀さん、三浦拓也さんはいずれも、焙煎士という枠を超えてコーヒー文化を進化させた存在と言えます。
坂口憲二
俳優として知られる坂口憲二さんは、病気による芸能活動の休止を経て“コーヒー焙煎士”として新たな人生を歩み始めました。
自身が立ち上げた「The Rising Sun Coffee」は、湘南の海沿いに店舗を構え、波の音とともにコーヒーを楽しむライフスタイルを提案しています。
坂口さんの焙煎スタイルは、浅煎りから深煎りまで幅広く、誰でも楽しめるバランスの取れた味づくりが特徴です。
彼は「コーヒーは人と人をつなぐもの」と語り、店舗を“コミュニティの場”として捉えています。芸能人という肩書きに頼らず、一人の焙煎士として真摯に豆と向き合う姿勢が多くの人々の共感を呼んでいます。
彼のブランドは単なるカフェではなく、“人生の再出発”を象徴する場所でもあり、焙煎士という職業の新しい可能性を示しています。
後藤直紀
福岡県の「豆香洞コーヒー」代表・後藤直紀さんは、2013年の「ワールドコーヒーロースティングチャンピオンシップ」で世界チャンピオンに輝いた、日本を代表する焙煎士です。後藤さんの焙煎哲学は「素材を生かす」ことにあります。
生豆を科学的に分析し、温度や時間の微調整を繰り返しながら、豆が持つ個性を最大限に引き出す“精密焙煎”が持ち味です。
また、後藤さんは教育者としても活躍し、全国の焙煎士やバリスタに技術指導を行っています。焙煎の標準化と再現性の向上を追求する姿勢は、日本のコーヒー品質を世界レベルに押し上げる原動力となりました。科学的な思考と職人的な情熱を併せ持つ後藤さんは、まさに“理論と感性を融合させた焙煎士”と言える存在です。
三浦拓也
「GLITCH COFFEE & ROASTERS」のオーナーである三浦拓也さんは、“浅煎りコーヒー”のブームを日本に広めた第一人者です。三浦さんの焙煎哲学は「豆が持つポテンシャルを信じる」こと。
酸味を恐れず、果実のような香りと透明感を引き出すことで、コーヒーの新しい魅力を提示しています。
彼の店舗は国内外から多くのファンが訪れ、世界中のバリスタや焙煎士との交流も活発です。その活動を通じて、“東京=コーヒー文化の発信地”という新しいイメージを築きました。
自由で実験的な姿勢を持ちながらも、常に“豆への敬意”を忘れない三浦さんは、焙煎士という枠を超えた文化の発信者です。次世代の焙煎士たちにも強い影響を与え続けています。
焙煎士の仕事内容
焙煎士の仕事は、単に生豆を焙煎するだけではありません。生豆の選定から焙煎プロファイルの設計、品質管理、時にはお客様への提供や教育まで、多岐にわたる役割を担っています。
コーヒーの味わいは、焙煎の工程で大きく左右されるため、焙煎士は“味づくりの最終責任者”ともいえる存在です。
さらに最近では、カフェや焙煎所のブランド戦略やマーケティングに関わるケースも増えており、ビジネス的な感覚も求められています。
機械的な作業というよりは、五感とデータを駆使した繊細な仕事であり、温度や時間を秒単位で調整しながら理想の味に近づけていく職人芸です。ここでは、焙煎士の代表的な仕事内容を3つに分けてご紹介します。
仕事内容①|生豆の選定と仕入れ
焙煎士の仕事は、生豆を選ぶところから始まります。コーヒーの味わいの7〜8割は生豆の品質で決まるとも言われており、どの豆を仕入れるかは非常に重要な判断です。豆の品種、産地、標高、精製方法、収穫年、保存状態など、多くの要素を考慮して選定を行います。
また、サンプル豆を取り寄せて試飲(カッピング)し、風味や香り、酸味・甘味・苦味のバランスを評価します。
最近では、生産者との直接取引(ダイレクトトレード)を通じて、持続可能な仕入れ体制を構築する焙煎士も増えています。品質を見極める舌と目を持ち、安定供給できる仕入れルートを築くことが求められます。

仕事内容②|焙煎プロファイルの設計と調整
焙煎士の中心的な業務が、焙煎プロファイルの設計とその実行です。焙煎プロファイルとは、加熱温度や時間、火力の強さやタイミングなどを数値化した“レシピ”のようなものです。豆の種類ごとに最適な焙煎プロファイルを設計し、風味を最大限に引き出すことが求められます。
焙煎中は豆の色や音、香りの変化をリアルタイムで感じ取り、データと経験をもとに微調整を加えていきます。数十秒の違いが味に大きく影響するため、集中力と感覚が重要です。
また、同じ味を再現できるように記録と分析も欠かせません。焙煎士は科学者のようにデータを扱いながら、アーティストのように味を創造していく存在です。
仕事内容③|品質管理とお客様への提供
焙煎後の豆が常に安定した品質であることを保証するのも焙煎士の重要な仕事です。焙煎直後だけでなく、時間の経過による変化も踏まえたチェックを行い、品質にばらつきが出ないよう管理します。また、ドリップやエスプレッソなど、抽出方法に応じた最適な焙煎を提案することもあります。
さらに、焙煎士が店舗に立つこともあり、コーヒーの魅力や味の背景をお客様に直接伝える機会もあります。生産地の情報や焙煎の工夫を丁寧に説明することで、ただの飲み物ではなく“体験”としての価値を提供できます。
教育者としてスタッフや顧客にコーヒーの魅力を伝える役割も担っており、焙煎士は技術者でありながらコミュニケーターでもあります。
焙煎士の年収・給料
焙煎士の年収は、勤務先や経験年数、スキルレベルによって大きく変わります。一般的に、焙煎士としてのキャリアをスタートしたばかりの方は年収250万〜350万円程度が相場とされています。
カフェやロースタリーでの勤務の場合、アルバイトや契約社員からスタートするケースも多く、初任給は月収20万円以下ということも珍しくありません。
一方で、経験を積み、焙煎士としてのスキルや実績が評価されるようになると、年収は400万〜600万円台に上がっていきます。特に、焙煎の責任者としてブランド豆の開発や品質管理を任されるポジションであれば、それ以上の収入も期待できます。
また、独立して焙煎所を開業した場合や、自家焙煎のカフェを経営するオーナー焙煎士になると、売上やブランド力次第で年収1,000万円を超えるケースもあります。
ただし、焙煎士は高収入よりも“やりがい”を重視する人が多い職種でもあります。収入を上げ
たい場合は、焙煎技術に加えて、ビジネススキルやブランディングの視点を身につけることが重要です。
焙煎士の求人を探す方法
焙煎士として働きたい場合、求人の探し方にも工夫が必要です。一般的な転職サイトでは「焙煎士」として明記されていないことも多く、職種名に「コーヒー製造」「ロースター」「製造スタッフ」などと記載されていることがあります。
そのため、焙煎士の求人を探すには、複数の視点から検索することが大切です。
また、近年はクラフト系やサードウェーブ系のロースタリーで人材を募集するケースが増えており、SNSや企業の公式サイトでの情報発信にも注目したいところです。
焙煎士の世界では、“現場での経験”が重視される傾向が強いため、未経験でも焙煎補助や見習いから入れる求人にアプローチするのも一つの方法です。ここでは、焙煎士の求人を見つけるための3つの具体的な探し方をご紹介します。
探し方①|コーヒー専門の求人サイトを活用する
焙煎士の求人を効率的に探すなら、まずは「コーヒー業界専門の求人サイト」をチェックすることをおすすめします。たとえば『CAFERES(カフェレス求人)』『グルメキャリー』『FoodJob Japan』などの飲食・専門職に特化したサイトでは、一般の転職サイトでは見つけにくいロースター求人が掲載されていることがあります。
また、「SCAJ(日本スペシャルティコーヒー協会)」のような業界団体のサイトでは、焙煎士やバリスタ向けの求人や研修情報も発信されています。
こうした専門サイトでは、求人票の内容もコーヒーへの理解が深く、職場の雰囲気や求められるスキルが具体的に記載されていることが多いため、ミスマッチを防ぎやすくなります。
探し方②|公式サイトやSNSから直接応募する
小規模なロースタリーや個人経営のカフェでは、大手の求人サイトを利用せず、自社の公式サイトやInstagram、X(旧Twitter)などのSNSで採用情報を発信していることがあります。特に「焙煎士見習い募集」や「アルバイトから社員登用あり」といった情報はSNS経由でのみ流れるケースも多いため、気になる店舗のアカウントはこまめにチェックしておくとよいでしょう。
また、コーヒーイベントやポップアップストア、マルシェなどで出店している焙煎所の担当者と直接つながることで、非公開の求人や見習いのチャンスを得られることもあります。
SNSやリアルなつながりを活用することで、ネットには出回らない「掘り出し求人」に出会える可能性があります。
探し方③|店舗へ直接問い合わせてみる
求人が公開されていない場合でも、「このお店で働いてみたい」と思えるロースタリーやカフェがあるなら、直接問い合わせてみるのも有効な方法です。特に、自家焙煎のカフェや焙煎所では、求人情報を常に発信しているとは限らず、タイミング次第で「ちょうど探していた」というケースもあります。
このような場合は、電話やメールで丁寧に問い合わせを行い、自分のコーヒーへの熱意や志望動機を簡潔に伝えると好印象です。履歴書や職務経歴書を添えて持ち込むことで、見学や面談の機会を得られることもあります。
焙煎士の世界では、形式よりも“やる気と姿勢”が重視されるため、自分から積極的にアプローチすることが就職への近道になることがあります。
焙煎士に関するよくある質問
焙煎士を目指す方や、コーヒー業界に興味のある方からは、進路や勉強方法、資格の有無などについて多くの質問が寄せられます。焙煎士はまだ一般的には馴染みが薄い職業ですが、専門性が高く、将来的には独立開業も目指せる魅力的なキャリアです。
その一方で、「どうやってなればいいの?」「何から始めたらいいの?」といった疑問を持つ方が多いのも事実です。
ここでは、焙煎士に関する代表的な3つの質問にお答えします。資格の有無やおすすめの勉強方法、有名な焙煎士、まで初心者の方にも分かりやすく解説しています。焙煎士への第一歩を踏み出したいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
焙煎士を目指すには資格があった方が良いですか?
焙煎士になるために、必須の国家資格や免許は存在しません。そのため、資格がないからといって焙煎士になれないということはありません。ただし、一定のスキルや知識を証明するための「民間資格」は存在しており、キャリアの初期段階や転職時のアピールには有効です。
代表的なものとしては、「コーヒーインストラクター検定」や「コーヒーマイスター」の各種資格などがあります。資格取得は必須ではありませんが、知識と信用を高める手段として有効です。

焙煎士になるのにおすすめの勉強方法はありますか?
焙煎士を目指すうえでの勉強方法には、大きく分けて「独学」と「スクール・実務経験」の2つがあります。まず独学では、焙煎に関する書籍やYouTubeの実践動画、オンライン講座などを活用できます。
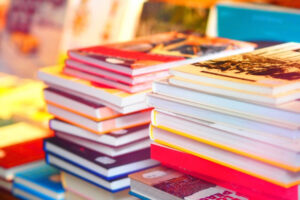
ただし、焙煎は“感覚”と“経験”がものを言う分野でもあるため、実機を触りながら学べる環境に身を置くことが重要です。
そのため、カフェやロースタリーで見習いとして働いたり、焙煎機メーカーのトレーニングに参加したりすることが、最短かつ効果的な学習法になります。知識だけでなく、実際に豆を焙煎し、五感で違いを感じることが、焙煎士への近道です。
世界一の焙煎士は誰ですか?
「世界一の焙煎士」と聞いて思い浮かぶのは、国際大会で実績を残したトップロースターたちです。とくに有名なのは、日本人として初めて「World Coffee Roasting Championship(WCRC)」で優勝した後藤直紀さん(豆香洞コーヒー)です。2013年の大会で世界一の座を獲得し、その技術力と分析力の高さが世界中で注目されました。
まとめ:焙煎士とは|必要な資格や仕事内容、坂口憲二を含む有名焙煎士も解説
焙煎士とは、生豆を焙煎してコーヒーの味と香りを創り出す専門職であり、職人であり、時にブランドの顔にもなる存在です。仕事内容は単なる焙煎作業にとどまらず、生豆の選定、焙煎プロファイルの設計、品質管理、顧客への提供や教育など多岐にわたります。
また、焙煎士という職業の魅力を広く知らしめた人物として、俳優から焙煎士へと転身した坂口憲二さんや、世界大会で優勝した後藤直紀さん、浅煎り文化を広めた三浦拓也さんといった、有名ロースターたちの存在も欠かせません。
焙煎士は、科学と芸術、そして情熱を融合させて「1杯のコーヒーに物語を宿す」仕事です。コーヒーに深い愛情を持ち、手に職をつけたい方にとって、焙煎士というキャリアは非常にやりがいのある選択肢だといえるでしょう。












コメント